- 救急外来で発熱や呼吸困難を主訴に搬送され、肺炎の診断で入院となる患者さんは非常に多いです。
- 肺炎の診断は実は難しく、重症度の評価がとても重要です。
- この記事では肺炎の診断方法や重症度の評価など、明日使える知識を紹介していきます。
肺炎かな?と疑うのはいつか
ずばり以下2つの場合に、「肺炎」を疑うべきです。
- ①敗血症、菌血症を疑う場合
- ②高齢者や誤嚥性肺炎を起こしうる患者さんでは以下のうち1つでも認めた場合
- 呼吸数増加
- 酸素化低下
- 発熱
- 意識障害
- 呼吸数は軽視されがちです。高齢者において呼吸回数が18回/分を超えている場合には要注意です。
肺炎の診断
肺炎は X線のみで診断してはいけない
- 頻呼吸や酸素化低下を認めないのに、胸部X線で肺炎像を認めるからといって肺炎と診断してはいけません。
- 脱水があると、画像で肺炎像がはっきりしないことがあります。
- 肺炎を疑う画像所見を認めても、以前から認めている陰影の可能性があります。
肺炎の診断にはバイタルサインや身体所見、聴診が重要
- 肺炎の初期症状は、咳や痰、発熱です(風邪と似ていますね)。その状態で、肺炎に至っているか否かの判断が必要です。
- その判断に使われるのが、Heckerling scoreやDiehr ruleがあります(HOKUTO様のページに飛びます)。
- 着目していただきたいのが、両者とも画像所見が含まれておりません。あくまで重要なのはバイタルサインや身体所見、聴診所見です。
- 画像所見は確認のために行います。
- バイタルサインや身体所見、聴診所見から肺炎を疑ったら、喀痰のグラム染色を行いましょう。
Heckerling score
| 項目 | スコア |
|---|---|
| 体温 > 37.8℃ | 1点 |
| 心拍数 > 100回/分 | 1点 |
| 呼吸音の減弱 | 1点 |
| 捻髪音(crackles)の聴取 | 1点 |
| 喘息がない | 1点 |
Heckerling scoreの合計点と肺炎の可能性 (事前確率5%)
- 0点:<1%
- 1点:1%
- 2点:3%
- 3点:10%
- 4点:25%
- 5点:50%
肺炎の重症度にはA-DROPやCURB-65が有用
- 現在の酸素投与量やSpO2だけで重症度を評価してはいけません。
- 重症度の指標としてA-DROPやCURB-65が有名です。
- Pneumonia Severity Index(PSI)もありますが、救急外来ではA-DROPやCURB-65が使いやすいです。
- A-DROPは本邦の高齢化を反映し、CURB-65よりも年齢設定が高くなっています。
- また、A-DROPは呼吸回数でなく、SpO2を採用しています。
A-DROP
| A-DROP | 基準(該当すると1点) |
|---|---|
| A(Age) | 男性 ≥ 70歳、女性 ≥ 75歳 |
| D(Dehydration) | BUN ≥ 21 mg/dLまたは脱水あり(臨床的脱水) |
| R(Respiration) | SpO₂ ≤ 90% または PaO₂ ≤ 60 Torr |
| O(Orientation) | 意識障害(見当識障害あり) |
| P(Pressure) | 収縮期血圧 ≤ 90 mmHg |
| A-DROPの合計点 | 重症度 | 治療方針 |
|---|---|---|
| 0点 | 軽症 | 外来治療 |
| 1~2点 | 中等症 | 外来 or 入院治療 |
| 3点 | 重症 | 入院治療 |
| 4~5点 | 超重症 | ICU入院 |
| ※ショックがあれば超重症 (ICU入院) |
CURB-65
| CURB-65 | 基準(該当すると1点) |
|---|---|
| C(Confusion) | 見当識障害や意識障害あり |
| U(Urea) | 尿素窒素(BUN)> 21 mg/dL |
| R(Respiration) | 呼吸数 ≥ 30 回/分 |
| B(Blood Pressure) | 収縮期血圧 < 90 mmHg または 拡張期血圧 ≤ 60 mmHg |
| 65(Age) | 年齢 ≥ 65歳 |
| Score | 重症度 | 治療場所 | 死亡率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 軽症 | 外来 | 0.7% |
| 1 | 軽症 | 外来 | 2.1% |
| 2 | 中等症 | 一般病棟 | 9.2% |
| 3~5 | 重症 | ICU | 15~40% |
「呼吸数」と「脱水」は特に重要
- 呼吸数と脱水の有無が特に重要です。
- 呼吸数は軽視されがちですが、SIRS criteriaに含まれているように重要です。
- なぜ脱水の評価が重要なのでしょうか?
- 初診時には酸素数リットルで問題なかったのにも関わらず、徐々に状態が悪化した経験はないでしょうか?
- これは、来院時に脱水の評価を正しく行っていないことが挙げられます。
- 肺炎によって透過性が亢進した肺に、不適切な量の輸液を入れることで、肺に水が漏れ痰が増え、呼吸状態が悪化するためです。
検査は【血ガス】・【グラム染色/培養】・【血液培養】を
血ガス
- 血ガスは「検査の三種の神器」のひとつです(他は心電図、エコー)。
- 酸素化・換気の評価だけでなく、乳酸値も必ず確認し、敗血症ショックか否かの判断を行います。
グラム染色/培養
- 脱水のため痰を採取することができない場合もありますが、可能な限り採取しグラム染色することが大事です。
- 高張食塩水(3〜10%の滅菌食塩水)をネブライザーで吸入し誘発することで痰を採取しやすくなります
- グラム染色でみえる病原体とみえない病原体があります。適切な痰を鏡検し菌が確認できれば細菌性肺炎、はっきりしなければ非定型肺炎と分けられます。
- グラム染色でみえる→肺炎球菌、インフルエンザ桿菌、モラクセラ・カタラーリス
- 肺炎球菌は鏡検上みえづらく、みえても貪食像がみられないことが多いです。
- みえなくても初回の抗菌薬はカバーすることが必要です。
- グラム染色でみえない→肺炎マイコプラズマ、クラミジア、レジオネラ
- 重症肺炎はレジオネラを疑います。
- レジオネラは通常の培地では発育しません(BCYE培地で発育)。よって、レジオネラ肺炎を疑っているときは検査室にその旨を伝えましょう。
- グラム染色でみえる→肺炎球菌、インフルエンザ桿菌、モラクセラ・カタラーリス
血液培養(入院適応のある場合)
- 肺炎は血液培養で陽性となる率は低いですが、米国のガイドラインでは以下の表の場合に血液培養の適応とされています。
| 市中肺炎における血液培養の適応 |
|---|
| ICU滞在 |
| 空洞形成 |
| 白血球減少 |
| アルコール多飲 |
| 重度慢性肝疾患 |
| 無脾症(解剖学的または機能的) |
| 肺炎球菌尿中抗原陽性 |
| 胸水貯留 |
- 原因菌の同定や治療期間の設定の2点からも、血液培養が必要です。
- 喀痰が採取できれば良いですが、上述のように難しい場合もあります。
- 血液培養が陽性となった場合に最低2週間の治療が必要となるため、血液培養は重要です。
尿中抗原
- 本邦では、肺炎球菌とレジオネラ肺炎の尿中抗原が使用可能です
- 感度は低いですが、特異度は高いです。よって検査が陰性だからといって否定してはいけません。
| 尿中抗原 | 感度 | 特異度 |
|---|---|---|
| 肺炎球菌 | 70% | 80~100% |
| レジオネラ | 74% | 99.1% |
- 注意点は偽陽性と偽陰性です。
- 肺炎球菌尿中抗原もレジオネラ尿中抗原も常に、既感染か新規感染かを考えないといけません。一度陽性となると数週間から数ヶ月排泄される可能性があるためです。
- また、肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス®)接種後は1週間程度陽性となると言われています。
- よって、病歴聴取や予防接種の有無の聴取が重要です。
市中肺炎の原因菌
- 市中肺炎の主な原因菌を表にしました。
| 細菌性肺炎 | 非定型肺炎 |
|---|---|
| ①肺炎球菌 | ④マイコプラズマ |
| ②インフルエンザ桿菌 | ⑤レジオネラ |
| ③モラクセラ・カタラーリス | ⑥クラミジア |
- 細菌性肺炎と非定型肺炎の違いも表にします。ここで注意なのがレジオネラ肺炎は含まれていないことです。レジオネラ肺炎については別記事にまとめます。
| 非定型肺炎の特徴(レジオネラ肺炎は含まれていない!) |
|---|
| 年齢60歳未満 |
| 基礎疾患がない、あるいは軽微 |
| 頑固な咳がある |
| 胸部聴診上所見が乏しい |
| 痰がない、あるいは迅速診断法で原因菌が証明されない |
| 末梢血白血球数が10,000/μL未満である |
| 条件 | 感度 | 特異度 |
|---|---|---|
| 6項目中4項目以上合致 | 77% | 93% |
| 5項目(1~5)中3項目以上合致 | 83.9% | 87% |
患者背景ごとの代表的な原因菌
- 患者背景によっては、考えなければならない原因菌が増えます。
- 誤嚥性肺炎については別記事でまとめます。
| 患者背景 | 代表的な原因菌 |
|---|---|
| アルコール多飲歴がある | 口腔内嫌気性菌、クレブシエラ |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 肺炎球菌、インフルエンザ桿菌、モラクセラ・カタラーリス、レジオネラ |
| ウイルス感染後 | 黄色ブドウ球菌、A群β溶連菌 |
治療
- 細菌性肺炎であればセフトリアキソン(CTRX)1〜2g ✕ 1回/日がfirst choiceになります。
- 肺炎球菌が疑わしければ、ベンジルペニシリン(PCG、ペニシリンG)を200万~400万単位 4時間ごと静注 または 1200万~2400万単位
- 非定型肺炎には、マクロライド系を使用します。結核を確実に否定できている場合に限りニューキノロン系を使用します。
- 細菌性肺炎+非定型肺炎といった重症肺炎であればCTRX 1〜2g ✕ 1回/日+AZM 500mg ✕ 1回/日(緑膿菌をcoverする必要があればCTRXの代わりに、PIPC/TAZ 4.5g ✕ 4回/日)
参考文献
以下の文献を参考にさせていただきまとめました。
- 感度と特異度からひもとく感染症診療のDecision Making 細川 直登 編
- 救急外来 ただいま診断中!第2版 坂本 壮 著
- Thorax. 2003 May;58(5):377-82

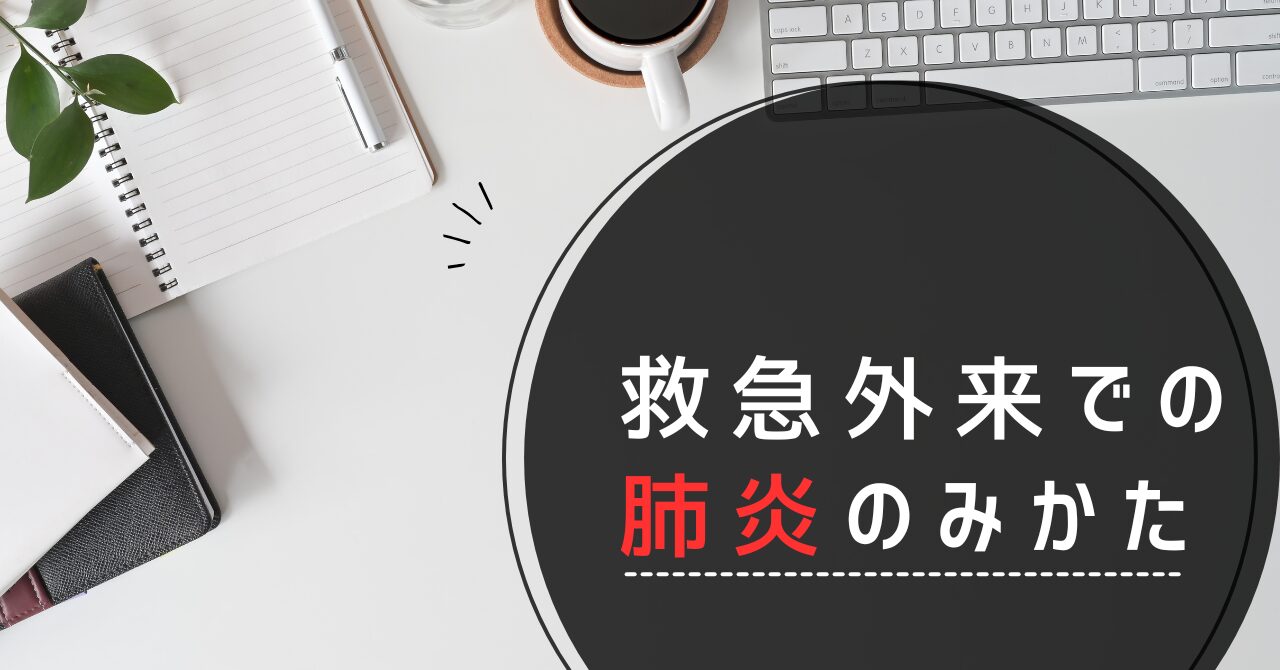


コメント